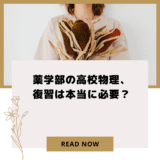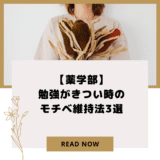※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。
- 薬学部の授業に集中するための予習術がわかる
- 試験前に焦らないための準備法が身につく
「授業中に集中できず、いつの間にか
置いてかれてる…。」
そんな経験はありませんか?
薬学部の授業では専門用語がバシバシ出てきて授業1回分の情報量も多く、
気を抜くとすぐに遅れを感じてしまいます。

気づいたら「何の話だっけ…?」と迷子になっていることも(笑)
そこで本記事では、授業にしっかりついていくための効率的な予習法を3ステップで解説しています。
今回紹介する予習法を実践することで、
授業に集中できるよう準備することができます。
- シラバスで授業の範囲を確認
- 教科書やネットで調べる
- わからない部分をリスト化
予習することで授業を受けた時の理解度が深まるので、
結果的に定期試験前の負担も軽減されます。
私自身も薬学生時代、さまざまな勉強法を試しながら、学年上位にいたこともあれば留年寸前まで落ちた経験もあります。
今回紹介する予習法は授業についていけない不安を払拭し、
自信を持って講義に臨めるようになる手助けとなるはずです。
授業の理解度を上げたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
こちらの記事は、授業についていけなくて悩んでいる時の対策について紹介しています。
 薬学部の授業が難しい?ついていけない時の対策5選
薬学部の授業が難しい?ついていけない時の対策5選
「授業についていけなくて、挫折しちゃいそう…。」と悩んでいる人は
こちらの記事もチェックしてみてください。
薬学部の授業で予習が大切な理由
授業についていけない理由とは
薬学部の授業は、とにかく専門的です。
高校までは聞いたことのない言葉が次々と登場し、予備知識が無いと何の話をしているのかわからなくなります。
理解が浅いまま授業を受けていると、
テスト前に焦ることになりがちです。

ちゃんと授業を聞いていればよかった…。なんて後悔をすることがあるかもしれません。
予習すれば授業の理解度が変わる
「ちょっと知ってる」だけでも
授業の聞こえ方はまったく違います。
事前に予習しておくことで「あ、これ見たことある!」という感覚が生まれ、
スムーズに話を理解できるようになります。
授業中に「この単語、この間やったところだ!」と思えると、
より集中して授業を受けることができます。

昔懐かしの「あ!ここ〇〇ゼミでやったところだ!」に近い感じですね。
(小中学校の時に漫画の宣伝チラシ見てた人多いはず!)
初見の内容ばかりよりも、少しでも予備知識がある方が授業に集中しやすくなるんです。
もし予習段階でわからなかった部分が授業中に「スッと理解できた」瞬間を体験できると、ヤバいです。(飛ぶぞ!)
その快感がやる気をどんどん引き出してくれます。

飛ぶぞ!
能動的に学ぶ姿勢が身につく
「ここの箇所がよくわからなかったから、今日の授業で解決したい!」
という気持ちを持って授業に臨むと、
ただ話を聞くだけの受け身の姿勢ではなく、「自分から学ぼうとする姿勢」が自然と育まれていきます。
このような積極的に学ぶ姿勢は
薬学部での勉強を深めるだけでなく、
薬剤師や研究者として将来働くときにも大きな力となり、周囲からの信頼にもつながっていきます。

積極的な姿勢は、学生のうちから身につけておくべきです!
試験勉強が楽になる効果も
予習をしておくと、結果的に試験前に詰め込む必要が減り
勉強の効率も格段にアップするのです。
- 授業中に「理解」が深まり、自分の中で内容を整理しながら知識を吸収できるように
- ノートの質や記憶の定着率が向上(ノート作り等でまとめ直す時間が減る)
- 余裕を持って復習に時間を使えるため、勉強全体の効率が大きくアップ
予習をしておくことで授業中に「理解」が深まり、自分の中でしっかりと内容を整理しながら吸収できるようになります。
その結果、ノートの質や記憶の定着率も向上し、試験前に慌てて知識を詰め込む必要が減少。
余裕を持って復習に時間を使えるため、勉強全体の効率が大きくアップします。
薬学部のように専門的な知識が多い学部では、この積み重ねが大きな差を生むのです。
授業が分かる予習術|3ステップ解説
薬学部の授業をしっかり理解するためには、事前の予習が欠かせません。
- シラバスで授業の範囲を確認
- 教科書やネットで調べる
- わからない部分をリスト化
ここでは
「授業の全体像を把握→重要ポイントを調べる→疑問を明確にして授業に臨む」
という3つのステップで、
効率的に授業内容を吸収するオススメ予習術を解説します。
ステップ1|シラバスで授業の範囲を確認
「予習と聞いても、まず何をすればいいのか分からない…。」
そんなとき、頼りになるのがシラバスです。
でも正直、しっかり読み込んだことがないという方も多いのではないでしょうか?
シラバスには授業のテーマや重要語句などが丁寧に書かれており、まさに「授業の設計図」のような存在です。
- その週に扱うテーマ
- キーワード(重要語句)
- 参考文献や使用する教科書
その授業で何を学ぶのか、どの範囲を扱うのかが網羅的に載ってます。
特にキーワード(重要語句)は必ずチェックするようにしましょう。(わざわざ「重要」って言ってくれてる!)

予習する時間が無い人も、シラバスは絶対にチェックするべきです!
こうした情報をあらかじめ確認しておくことで、予習の方向性が明確になります。
「何を準備すればいいのか分からない…」という不安もなくなりますよ。
ステップ2|教科書やネットで調べる
次に、シラバスで確認した範囲を教科書やインターネットでざっくり調べてみましょう。
ここでの目的は「完全に理解すること」ではなく、「何となくでも良いから、内容を知っておくこと」です。

授業で出てきたときに、「あ~、この間調べたところだ。」くらいの温度感で大丈夫です。
私自身、予習する時は次に挙げるような
やり方でやっていました。
- シラバスに出てきた単語の意味を調べる
- 重要語句や解らない部分は、付箋を貼るなどマーキングしておく
教科書だけでは解らないことも出てくると思います。
その場合はインターネットなども積極的に使いましょう。

ググってみると、わかりやすく解説してくれているサイトに辿りつくこともあります。
ステップ3|わからない部分をリスト化
予習しても「ここ、意味不明だな」というところ、出てきますよね。
そういう場所こそが、皆さんにとっての「学びのチャンス」です。
- わからない箇所をリストアップ
- 授業中にその答えが出てくるか注目する
- 出てこなければ、授業後に先生に質問する
わからなかった部分はノートの端に「疑問リスト」としてメモしておきましょう。
そして授業中、その答えが説明されるかに注目してみてください。
あらかじめ“解決したいこと”があると、自然と授業への集中力が高まります。
しかも自分の中で「理解の穴」をつぶしていくことで、
その後の復習効率もアップし
知識がしっかり定着するようになります。

もし授業で解決できなければ、授業後に思いきって先生に質問してみるのもおすすめです。
まとめ:薬学部 授業が分かる予習術3ステップ
薬学部の授業は難しかったり、
気を抜いていると置いてかれることが多いです。
でも「授業を受ける前に、ほんの少し準備する」だけで、
その内容はグッと理解しやすくなります。
今回ご紹介した3ステップは、
どれもすぐに始められるものばかりなのでオススメです。
- シラバスで授業の範囲を確認
- 教科書やネットで調べる
- わからない部分をリスト化
時間が無ければ、シラバスに載っている重要語句をググってみるだけでもだいぶ違ってくると思います。
この流れを続けていけば、「授業がわかる」→「テストが怖くない」→「勉強が前向きになる」という好循環が生まれます。
ぜひ、今日から試してみてください!
以上、「【薬学部】 授業が分かる予習術3ステップ」という話題でした!