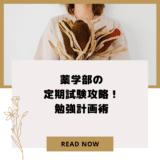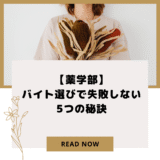※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。
- 科目ごとに時間配分を決めるコツ
- 無理のないスケジュールを作る工夫
- 復習を取り入れた効果的な計画法
- 落とせない科目に集中する優先順位のつけ方
- 継続できる学習習慣を作る方法
薬学部の定期試験は、次の2つが悩みのタネになりがちです。
- 勉強量の多さ
- 科目によって難易度に差があること
- 「時間が足りない」
- 「どこから手をつければいいかわからない」
こういった不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?
結論からお伝えすると、
「復習を前提にした無理のないスケジュールを立て、調整日を確保すること」が成功のカギです。
筆者は、薬学生時代にさまざまな勉強法を試し、学年上位から留年寸前まで幅広い成績を経験しました。そんな経験をもとに、試験前でも心に余裕が持てるスケジュールの立て方をまとめました。
今回の記事は、特にこんな方におすすめです
- 計画を立てても途中で崩れてしまう
- 難しい科目にどう時間を割けば
よいか悩んでいる - 試験直前になると焦って手につかなくなる
記事の前半で「薬学部の定期試験は大変」と言われている理由について解説し、
後半では勉強のスケジュール作成にあたっての注意点について解説しています。
勉強のスケジュール作成にあたって注意することは、下の通りです。
- 科目ごとの難易度を見て勉強時間を調整する
- 落とせない科目から優先順位をつける
- 「調整日」があることを前提にスケジュールを組む
- 復習の機会を必ずスケジュールに組み込む
- ToDoリストを活用する
- 毎日コツコツ続けられる工夫を
読み終えたときには、「これなら自分でも続けられそう!」と思える勉強計画のコツがきっと見つかります。
ぜひ、最後まで読んでみてください。
薬学部の定期試験はなぜ大変なのか?
範囲が広く暗記量が多い
薬学部の試験は、とにかく覚える量が
膨大。
物理化学・有機化学・薬理・薬剤など、1つ1つの科目だけでも広い範囲をカバーしなければなりません。

しかも単なる暗記だけではなく、理解力や応用力も求められます。
試験が連続していて科目数も多い
テスト期間は、1~2週間のあいだに10科目以上が詰め込まれることも珍しくありません。
1つの試験が終わってもすぐ次の準備…と気持ちの切り替えも大変です。
直前に詰め込んでも、
「勉強したのに点が取れない…」
なんてことも。

勉強計画作りに失敗すると、こういった悲劇もありえます。
ちなみにですが、
薬学部の試験勉強でオススメできない
勉強法というのがあります。
そういった勉強法については、
こちらの記事で紹介しています。
 つらいテストを乗り切る!薬学生が避けたい落とし穴3選
つらいテストを乗り切る!薬学生が避けたい落とし穴3選
試験期間に入る前に確認できれば、試験勉強で失敗する確率を下げることができます。
心配な人はチェックしてみてください。
高得点を取らないと再試・留年のリスク
薬学部のテストは、合格点を切ると容赦なく再試験です。
さらに再試も落とすと留年の可能性も出てきます。
そのため、「絶対に落とせない」というプレッシャーの中で戦わなければならないのです。

このプレッシャーに潰されて、自分を見失ってしまう人も。
スケジュール作成のコツと注意点
定期試験を乗り切るには、「計画の立て方」を正しく身につけることが何より重要です。
ここでは、勉強スケジュール作成のコツと注意点について解説します。
① 科目ごとの難易度を見て勉強時間を調整しよう
まずは試験を受ける全科目をざっと確認し、それぞれの難易度や性質を把握しましょう。

それぞれの科目で必要な勉強時間を、ざっくりでもいいので見積もってみましょう。
薬学部の科目には、「暗記だけで乗り切れるもの」と「理解が必要なもの」の両方があります。
例えば有機化学や物理化学などは、構造や反応機構をしっかり理解しないと点数につながらないため
まとまった勉強時間を確保する必要があります。
一方で、内容が覚えやすい範囲に限られている科目や普段からコツコツ勉強していた科目は
直前の数日でなんとか形にできる可能性もあります。

「理解が必要な科目」や「暗記量が多い科目」は、勉強時間を多めに見積もっていた方が良いです。
こういった科目を事前に見極めることで、全体のスケジュールにメリハリをつけることができます。
- 「理解系の科目」や「暗記量が多い科目」は時間多めに確保(例:有機化学など)
- 「範囲が狭い科目」や「普段から勉強していた科目」は時間少なめでOK
- 各科目の特性を見て、配分のバランスをとる

全部の科目を同じ熱量でやるのではなく、メリハリをつけるのが計画のコツです!
これに加えて自分の得意・不得意や科目の特徴に合わせて勉強時間を調整すれば、
限られた時間でも効率よく対策ができます。
② 優先順位をつけて計画しよう(落とせない科目から)
試験前は時間との勝負。
全科目をまんべんなく勉強するのは現実的ではありません。
そこで重要なのが、
“優先順位をつける”ことです。
先ほど「①科目ごとの時間配分を決める」と紹介しましたが、
優先順位もつけておくと計画を立てやすいです。
- 再試になると問題の難易度が難しくなる科目(再試にしたくない科目)
- 留年や進級に直結する必修科目
- 苦手な科目

落としたらまずい科目は、早め&多めに対策するのが鉄則です!
一方で、点数を取りやすい科目や自信のある科目は「最低限の時間で確実に取る」という戦略でOKです。
- 落とせない科目 → 時間をしっかり確保
- 得意科目・軽めの科目 → 効率重視でいく。短時間で対策。
このようにリスクと効率のバランスを考えて時間配分することで、
限られた時間でも効果的な試験対策ができます。
③ 無理のない範囲で計画をたてよう
試験勉強の計画を立てるときは、
まず試験日程を確認し、そこから逆算して勉強のペースを決めていきます。
このとき大切なのは、
予定を詰め込みすぎないことです。
1日10時間勉強するのが可能な人もいますが、大切なのはそのペースを継続できるかどうかです。
計画倒れにならないためにも、
少し余裕のある計画作りが重要です。
- 予定を詰め込みすぎない
- ずっと同じ科目を続けず、
科目はこまめに切り替える - 週に1〜2日は調整日を確保する

勉強って、予定通りに進まないんですよね…。だから調整日があると本当に安心!
実際、体調の変化や思ったより時間がかかるといった理由で、計画通りに進まないことの方が多いのが現実です。
そんなときに調整日があれば、
遅れを取り戻せたり気持ちをリセットできたりとメンタル面でも安心感が生まれます。

スケジュールは詰め込むより“崩れにくく設計する”ことが大切です。
調整日を上手に活用して、
柔軟に対応できる計画を目指しましょう!
④ 復習タイムを必ずスケジュールに組み込もう
勉強は「やったら終わり」ではありません。
1回インプットしただけでは、知識はすぐに抜けてしまいます。
脳に定着させるには、
時間を置いて繰り返し復習することが必要です
- 脳は使わない情報をすぐ忘れる
- 「思い出す」ことで記憶が強化される
- 復習を繰り返すほど、ミスや理解不足に気づける

1回で覚えられなくても大丈夫!何度も復習することが大事です。
おすすめは、
時間をずらして何度も復習することです。
- 1回目:インプット(講義ノートや教科書を覚える)
- 2回目:翌日〜2日後にアウトプット(問題を解く)
- 3回目:試験1週間前に最終チェック
上記のように何度も復習することで
理解の浅い箇所が浮き彫りになり、試験前の見直しがグッと効率的になります。
そして、 復習の時間もあらかじめ計画に組み込んでおきましょう!
復習は時間が余ったらやるのではなく、最初からスケジュールの一部にすることで確実に実行できます。

復習をおろそかにしていると、あとで痛い目をみます。
復習するタイミングについては、次の記事で詳しく解説しています。
 薬学生の勉強効率UP!最適な復習スケジュールとは
薬学生の勉強効率UP!最適な復習スケジュールとは

復習スケジュールの管理方法についても解説しています!
⑤ ToDoリストで可視化しよう(アプリや手帳を活用)
勉強計画を頭の中だけで管理するのは
非効率です。
忘れたり後回しになったりして、気づけば何をすればいいか分からない状態になりがちです。
そんな事態を防ぐには、ToDoリストを使って「今やるべきことを可視化する」ことがカギです。
- やるべきことが明確になる
- 達成感が得られ、モチベーションUP
- 予定の遅れに気づけて、早めに軌道修正できる

今日は何をやるかがパッと見えるだけで、頭がスッキリして集中しやすいです!
特におすすめなのが、
毎日ToDoリストを作る習慣を身につけることです。
その日にやるべき課題が明確になるので、「何から手をつけよう…」と迷わずにすみます。
- 今日の勉強範囲・課題が明確に
- どこまで終わらせるかのゴールが見える
- 時間配分や優先順位の意識が高まる
- 集中しやすく、取り組みやすい
🛠 ToDoリストを作るための
おすすめツールと特徴
以下のようなツールを使うと、
計画が可視化されて毎日の勉強管理が
グッと楽になります。
| ツール | 特徴 |
|---|---|
| 紙のスケジュール帳 | 全体を俯瞰しやすく、手書きで記憶にも残る |
| Googleカレンダー | リマインダー機能で予定忘れ防止、PC・スマホ両対応 |
| Studyplusなどの学習アプリ | 勉強時間の自動記録&進捗管理ができて達成感◎ |
自分に合った方法を選びましょう。
試験直前は「何から手をつければいいかわからない…」と焦ることもあります。
そんなときにToDoリストがあれば、迷わず行動できるようになります。
スケジュールを可視化することで、
やることが整理され、勉強への集中力もグッと上がります。

スケジュールを頭の中だけで管理するのはNGです。
⑥ 毎日コツコツ続けられる工夫をしよう
どれだけ綿密な勉強スケジュールを立てても、実行できなければ意味がありません。
大切なのは「無理なく続けられる仕組み」を自分の中に作ることです。

特別な努力よりも、小さな習慣の積み重ねが試験本番での自信につながります。
例えば、次のような行動を日常に組み込んでみましょう。
- 朝15分だけ、前日の復習を行う
- 1日1問だけでも過去問に触れる
- スタディタイマーやポモドーロ法を活用して集中時間を意識
- 勉強時間をアプリやノートで記録する

「今日もやれた」という成功体験を毎日積み重ねる方が大事です!
これらの工夫を取り入れることで、「今日は何をすべきか」が自然と明確になります。
やることが明確だと迷いが減り、勉強への集中力も高まります。
また、ToDoリストにチェックを入れるだけでも「前身できている感覚」が得られ、やる気の維持に効果的です。

大きな目標よりも、日々の小さな達成感を積み重ねていくことを意識しましょう。
まとめ:【薬学部】定期試験の勉強計画を立てるコツ
薬学部の定期試験は、内容が広くて覚えることもたくさんあります。
ですが、しっかりとした計画を立てて行動すれば、不安はぐんと減ります。
この記事で紹介したポイントをおさらいしましょう。
- 難しい科目には、しっかり時間を取る
- 無理に詰めこまず、ゆとりある予定を作る
- 復習の時間をあらかじめ入れておく
- 大事な科目には優先的に取り組む
- ToDoリストなどでやることを見えるようにする
- 毎日少しずつでも続けられる工夫を取り入れる

毎日順調にいくとは限らないです。だからこそ、調整日を作っておきましょう!」
一番大切なのは、自分にとって無理のない計画を立てることです。
そして「少しずつでも前に進めている」という実感をもつことが、やる気につながります。
薬学部での勉強を進めていくと、気づかないうちに教科書・参考書・ノート類などの荷物がどんどん増えていきます。
試験のたびに新しい教材が必要になる一方で、もう使わなくなったものが机の上や本棚に溜まっていくことも少なくありません。

そのまま放置しておくと、何が必要で何が不要なのか分からなくなり、勉強の効率も下がってしまいます。
そこで、学習環境をスッキリ整えるための「断捨離のコツ」をまとめた記事をご用意しました。
教科書やプリント、過去問などの整理に悩んでいる方は、ぜひこちらも参考にしてみてください。
 薬学部の教科書を処分したい!捨てる・残すを決める方法
薬学部の教科書を処分したい!捨てる・残すを決める方法
試験に向けて焦る気持ちもあるかもしれませんが、コツコツ続ける力がいちばん強い武器になります。
今日から少しずつ、一緒に前に進んでいきましょう!
以上、「【薬学部】定期試験の勉強計画を立てるコツ」という話題でした!