※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。
- 薬学部の期末試験で失敗しやすい勉強法とその改善策
- 過去問の正しい活用法
- 復習を効率よく進めるスケジュールと優先ポイント
- ノート作りを効率化し、覚える時間を確保する方法
期末試験を前にして、
「この勉強法で本当に大丈夫かな…。」
と不安になっていませんか?
私自身、薬学生時代にさまざまな勉強法を試し、学年上位から留年の一歩手前まで色々な成績を取ってきました。
その中で気づいたのは、
間違った勉強法では、頑張っても結果がなかなかついてこない という事実です。
この記事では、
薬学部の期末試験でよくある勉強法の落とし穴を具体的に解説し、試験で成功するための実践的な改善策を紹介します。
例えば、こんな悩みに心当たりはありませんか?
- 過去問だけを頼りにしていて不安が残る
- 一度勉強した内容を復習せず、そのままにしてしまう
- ノート作りに時間をかけすぎて他の勉強が進まない
これらの悩みを放置すると、試験の点数に悪影響を及ぼすだけでなく、モチベーションも低下します。
悩みを抱えたままだと、イマイチ勉強に集中できないので、悪循環です…。
でも、安心してください!
この記事を最後まで読めば、 自信を持って期末試験に臨むための勉強法 を学ぶことができます。
期末試験で成功するためには、 ついついやりがちな間違った勉強法を避けること が不可欠です。
具体的には
- 過去問を効率的に活用し、本質を理解する
- 記憶に残る復習スケジュールの作り方
- ノート作りを簡略化し、覚える時間を増やす工夫
これらのポイントを押さえれば、試験対策が驚くほどスムーズに進むはずです。
勉強法に迷いがある方こそ、この記事を最後まで読んで、成功への一歩を踏み出しましょう!
過去問だけで対策を済ませる危険性

期末試験に落ちまくっている人の特徴としてよくあるのが、
「過去問で出た箇所しか勉強しない」です。
過去問だけで勉強を終えてしまうと、試験本番で予想外の問題に対応できず失敗するリスクがあります。
本質的な理解を深めることが成功の鍵です。
過去問の限界を知ろう
過去問は出題傾向を把握する上で非常に便利なツールです。
試験勉強を始める時、まずは過去問の確認から始める人も多いと思います。
しかし、過去問の活用については以下のような注意点があります。
- 過去問に出た範囲だけでは網羅できない
- 試験範囲が広い場合、過去問には無かった重要な内容が試験に出題されることがあります。 - 問題の応用力を試すケースに対応できない
- 同じテーマでも、異なる視点や応用力を問われる問題が出される場合があります。 - 出題形式の変更に対応できない
- 教授が試験の形式を突然変えることもあり、過去問に頼りすぎると対応できない可能性があります。
過去問だけの勉強だと、どうしても限界があります。
過去問を活用する際は、「試験の一部を把握するための参考資料」として使い、
全てを網羅するものではないと理解することが重要です。
過去問だけで済ませる勉強法は、合格への大きなリスクになりかねません。

過去問を過信しないようにしましょう! テストの作成者は、ある日突然裏切ってきます(笑)
本質的な理解が必要な理由
薬学部の試験では、単に暗記するだけでは対応できない問題が多く出題されます。
本質的な理解を深めることで、どんな問題にも柔軟に対応できる力を養えます。
本質的な理解が必要な理由は、以下の通りです。
- 関連知識を組み合わせる力が必要とされてきている
- 国家試験では複数の分野を結びつけて考える問題が出ることが多いです。
基礎から応用まで理解していると解ける問題が増えます。 - 長期的な知識の定着
- 表面的な暗記では試験後に忘れてしまう知識も多くなります。本質を理解することで、記憶が長持ちします。 - 実践で使えるスキルを習得できる
- 将来、薬剤師として働く際にも役立つ知識を身につけるためには、しっかりとした理解が欠かせません。
近年の国家試験では、複数の分野を結び付けて大問として出題する傾向にあります。
薬剤師の資格を取りに行く以上、国家試験を避けては通れないので、今のうちから準備しておくする必要があります。
学校によっては、国家試験で出題されることを踏まえ
今後の定期試験でそういった問題を出題されるようになってくるかもしれません。
「じゃあ、どうやって準備するの?」についてですが、
- 「習ったことを本質的に理解する」
これに尽きます。
テスト前に丸暗記したことは、割とすぐに忘れてしまいます。
本質的に理解していると、ちょっと勉強し直せばすぐに覚え直せるので、ちゃんと勉強しましょう!
過去問に取り組む前に、教科書や講義資料を活用し、基礎的な内容を深く理解しておくことが重要です。
その上で過去問を使えば、得点力も一層高まります。
一度きりの学習で復習を怠るミス

勉強した後、復習はやっていますか?
一度勉強しただけで満足し復習を怠ると、記憶が薄れて本番での得点力が低下します。
余程優秀な人でない限り、何回もやらないと記憶が定着しません。(たま~に天才がいるけど、その人達は無視で!)
勉強内容を定着させるためには、計画的な復習が重要です。
記憶を定着させるための復習スケジュール
勉強した内容を確実に記憶に残すには、適切なタイミングでの復習が欠かせません。
試験直前に慌てることなく準備するためにも、以下のようなスケジュールを取り入れましょう。
- 1日後に復習する
- 勉強した翌日に復習を行うことで、短期記憶を長期記憶に移行させやすくなります。 - 1週間後に再確認する
- 定着した知識が、まだ記憶に残っているかを確認するタイミングです。
忘れている部分があれば補強しましょう。 - 試験前にまとめて総復習する
- 試験直前には全体を見直し、重要ポイントを再確認して自信をつけます。
このように、複数回に分けて復習することで、効率よく記憶を定着させることができます。
一度の勉強で終わりにせず、計画的に繰り返すことが成功の鍵です。
勉強の復習スケジュールについては、こちらの記事で詳しく解説しているので、
気になる方はこちらの記事もチェックしてみてください。
 薬学生の勉強効率UP!最適な復習スケジュールとは
薬学生の勉強効率UP!最適な復習スケジュールとは
復習のコツ|優先すべきポイントとは?
復習は全てを繰り返す必要はありません。
効率を高めるために、以下のポイントを優先しましょう。
- 試験範囲の中で重要な箇所を復習する
- 教授が強調していた内容や、過去問で頻出のテーマに集中しましょう。 - 苦手な分野を重点的に確認する
- 自分が覚えにくい内容や理解が曖昧な部分をしっかり復習することが大切です。 - 問題を解きながら復習する
- 実際に問題を解いて知識をアウトプットすることで、より効果的に定着します。

3つ目の「問題を解きながら復習する」については、
そもそも問題が無かったり、自分で問題を作る時間が無ければ、サッと目を通すだけでも大丈夫です。
復習の際は重要な部分を優先し、時間を有効に使いましょう。
効率よく進めることで、全体の勉強バランスも整います。
ノートまとめに時間を割きすぎる落とし穴
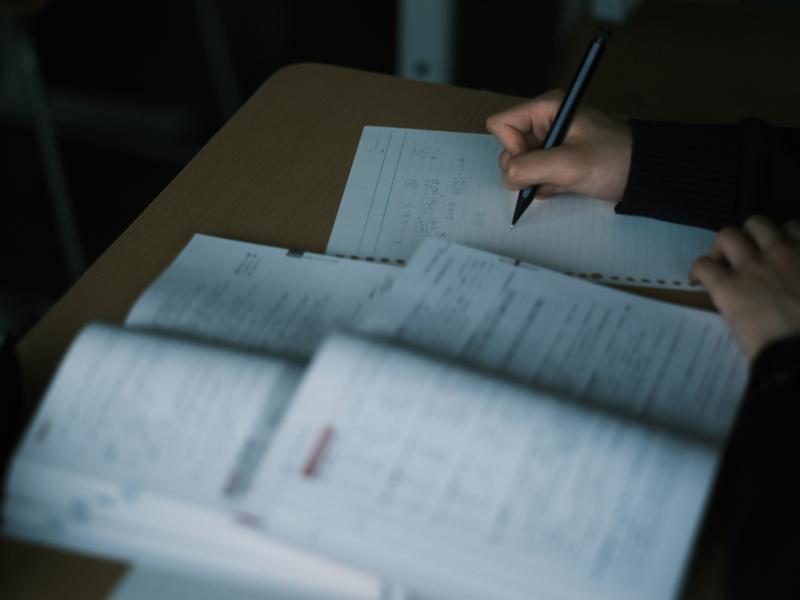
試験勉強を行うにあたって、試験範囲の内容をノートにまとめ直す人は多いと思います。
しかし、ノート作りには「時間がかかる」という落とし穴があります。
ノート作りに時間をかけすぎると、
肝心な内容の理解や暗記に時間を使えず、結果的に試験で失敗する可能性があります。
ノート作りに時間をかけすぎるリスク
ノート作りは、こだわりだすとキリが無いです。
ノートをきれいにまとめることに夢中になってしまうと、以下のようなリスクがあります。
- 学習時間の配分が偏る
- ノート作りに多くの時間を使いすぎると、理解や暗記、問題演習に十分な時間を確保できなくなります。 - 内容を「書く」ことが目的化する
- ノートを整理することばかりに集中すると、試験で問われる本質的な理解がおろそかになります。 - 試験直前に慌てる原因になる
- ノート作りが進んでいても、理解が浅いままだと試験準備が整わず、不安が募る結果になりがちです。
ノート作りは大事ですが、それに時間をかけすぎると肝心な学習がおろそかになるリスクが高まります。
試験勉強ではバランスが大切です。

ノート作りにこだわってしまうと、時間が無限に溶けていきます。
どうしてもこだわりたい場合は、普段からノート作りに取り組むようにしましょう。
理解と暗記の時間を優先する工夫
ノート作りよりも、理解や暗記に時間を割くためには工夫が必要です。
ここでは、ノート作りに時間をかけすぎないようにするためのコツを紹介します。
- ノート作りの時間を制限する
- ノートを作る時間を1科目あたり30分などと決めることで、他の学習に時間を割けます。 - 要点を中心に記録する
- 細かく書きすぎず、重要なキーワードやポイントだけを記録するスタイルを意識しましょう。 - すぐに復習できる形を整える
- ノートを作ったらすぐにそれを使って内容を覚える練習を行い、理解を深めます。
ノート作りを効率化することで、他の勉強に使える時間を増やせます。
この工夫が試験勉強の質を高める鍵です。

ノート作りは、あくまでも作業です。
内容の理解や暗記に、たくさんの時間と労力を割くようにしましょう!
どうしてもノート作りにこだわりたい、時間を割きたいという人は、
他の人よりも早いうちから準備を始める必要があります。
よく、薬学部の定期試験の準備期間は「試験1か月前から」と言いますが、
ノート作りにこだわるのであれば、2か月以上前から始めるのをオススメします。
(ホントは、普段からやっておくのが理想です(笑))
こちらの記事では、試験勉強をいつから始めるべきかという話題について紹介しています。
気になる方はチェックしてみてください。
 薬学部のテスト勉強、いつから始めるのが正解?
薬学部のテスト勉強、いつから始めるのが正解?
効率的なノート活用と覚える方法
作ったノートを最大限に活用するためには、
以下の方法を試してみましょう。
- 重要な語句を隠してチェックする
- ノートに書いた内容を紙や付箋で隠しながら、思い出せるか確認する勉強法です。 - 問題演習と組み合わせる
- ノートで覚えた内容を、実際の問題に当てはめて解くことで知識が定着します。 - ノートを繰り返し見直す
- 一度作ったノートを放置せず、何度も見直して復習に使うことで効果が上がります。
効率的なノート活用は、覚えるための最強の武器になります。
ただ作るだけで終わらせず、しっかり使い込むことがポイントです。

せっかくノートを作ったなら、使い倒しましょう!
まとめ:【薬学部】期末試験|失敗しがちな勉強法3選
この記事では、薬学部の期末試験においてよくある勉強法のミスとそれを避けるための実践的な方法を紹介しました。
学習効率を高め、試験に自信を持って臨むためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
- 過去問だけに頼らない
- 過去問は試験対策に有効ですが、それだけでは本質的な理解が深まりません。
過去問を解くときには、必ずその背後にある原理や理論を理解することが必要です。 - 復習を怠らない
- 一度勉強しただけでは記憶は定着しません。復習は定期的に行い、知識を強化することが大切です。
復習のタイミングと方法を計画的に決め、効率よく進めましょう。 - ノート作りに過度に時間をかけない
- ノート作りに時間をかけすぎて、他の勉強が進まなくなってしまうのは本末転倒です。
重要なポイントを押さえた簡潔なノートを作り、その内容を理解し暗記することを優先しましょう。
これらの勉強法を実践することで、自信を持って試験に臨めるようになります。
勉強方法に悩みがあった方も、これらを参考にして試験対策を進めてみてください。
ところで、試験が終わった後に使用済みの教科書をどうするべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
保管するのか、処分するのか迷うところですよね。
特に「簡単かつお得に処分する方法」を知りたいという声もよく聞きます。
そこで、 教科書を賢く処分する方法 をまとめた記事をご用意しました。
この記事を参考にして、使い終わった教科書を有効活用しましょう!
 薬学部の教科書を賢く処分|売却の完全ガイド
薬学部の教科書を賢く処分|売却の完全ガイド
今回紹介した、失敗しやすいテスト勉強法に注意することで、
期末試験で失敗する可能性を減らすことができます。
いずれも、私が試験勉強で上手くいかなかったときにやってしまっていたことです。
みなさんは、私の二の舞にならないように気をつけてください!
以上、「【薬学部】期末試験|失敗しがちな勉強法3選」という話題でした!



