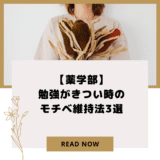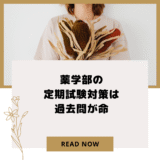※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。
- 薬学部の定期試験に合格するための“本当に必要な勉強法”がわかる
- 効率よく勉強するために意識すべきことが学べる
定期試験の勉強は
なんとなくやっていませんか?
薬学部は覚えることが多いです。
そのため勉強法を間違えると、
どれだけ努力しても結果が出にくいのが
薬学部の怖いところです。
この記事では、
薬学部の定期試験に「確実に合格する」
ために必要な勉強の鉄則を3つに絞って
ご紹介します。
筆者は、薬学生時代にさまざまな勉強法を試し、学年上位から留年の危機までを
味わってきました。
だからこそ断言できます。
正しい戦い方(勉強法)を知るだけで、結果は劇的に変わります。
- 「この勉強法で大丈夫かな…」
- 「もっと効率のよい方法があるんじゃないか」
そんな不安を感じている方も
読み終える頃には
やるべきことが明確になり、
迷いがスッと晴れるはずです。
この記事では以下のような流れで、
薬学部の試験対策を深掘りしていきます。
- 鉄則①:過去問の活用法(出題傾向の把握と対策の絞り込み)
- 鉄則②:シラバスの活用法
(“出る内容”を事前に見抜く) - 鉄則③:授業中の行動
(合否を分ける日々の小さな習慣)
「頑張っているのに点が取れない」
そんなもどかしさを感じている人にこそ、最後まで読んでいただきたい内容です。
試験本番で合格できる勉強法を
一緒に見直していきましょう。
正しい勉強方法が分かっていても、時間が足りなければ試験に落ちてしまいます。
次の記事では、
「テスト勉強をいつから始めるべきか」について解説しています。
 薬学部のテスト勉強、いつから始めるのが正解?
薬学部のテスト勉強、いつから始めるのが正解?

気づいたら、時間が足りない…(泣)。
なんてことにならないようにしましょう!
こちらの記事は冒頭で触れた、
「やってはいけない勉強法」について
解説しています。
自分が当てはまっていないか心配な人はこちらもチェックしてみてください。
 つらいテストを乗り切る!薬学生が避けたい落とし穴3選
つらいテストを乗り切る!薬学生が避けたい落とし穴3選
鉄則① 過去問を最大限に活用する
過去問は試験のヒントが詰まっている
定期試験の最重要アイテムといえば
過去問です。
なぜ過去問が重要かというと、
出題者が例年と同じ場合は過去問と
似たような問題が予想されるためです。
教授は自分の研究や論文作成などで忙しい人が多いので、試験問題の作成に多くの時間を割けません。
そのため試験問題は過去の問題を使い回したり、内容を少しだけ変えて出題されることも多いです。

ひどい時は全く同じ問題が出ることもあります。(笑)
例えば
- 定義を問う問題が毎年出る
- 数値を変えただけの同じ計算問題
といった具合で、同じパターンが繰り返されることが多いです。
過去問を解くことで、どこが大事なのかを効率的に把握できます。
どこで手に入れる?誰に聞く?
「過去問なんて持ってない…」という方も大丈夫です。
- 先輩からもらう
- 友人と共有する
など、意外といろいろな入手ルートがあります。

たまに先生が過去問を配ってくれることも!控えめに言って神。
解くだけでなく、出題意図を考える
「とりあえず解く」だけで終わるのは
もったいないです。
大事なのは、
なぜこの問題が出るのかを考えること。
教授が伝えたい“理解してほしい核心”を
つかむことができれば、真新しい問題にも対応できるようになります。
シラバスや授業スライドと照らし合わせながら過去問を分析すると、より深い学びになります。

出題意図は後で紹介するシラバスにヒントがちりばめられています。
鉄則② シラバスを制する者が試験を制す
シラバスには「出題のヒント」が詰まっている
意外と見落とされがちなのが、
シラバスの存在です。
実は、
教授が「この授業で何を学んでほしいか」を明確に書いてある超重要資料なんです。
- 到達目標
- 評価方法
- 試験で重視するキーワード
シラバスには単位をとるために必要なことが全て書かれていて、出題内容の
“設計図”のような存在とも言えます。

シラバスをチェックしておかないのは、非常にもったいないです!
試験前だけでなく授業初期から意識すべき
多くの人は試験直前に慌てて読むと思いますが、実は授業の初期から何度も目を通しておくと非常に効果的です。
例えば、習得目標に
「薬の作用機序を説明できる」とあれば
それを意識しながら授業を受けることで、学びがグッと深まります。
重要ワードをマーカーで囲っておくなど、早めの準備が合格への近道です。

なんとなく話を聞くのと違い、課題を持って授業に臨んだ方が集中できますよ!
次の記事で日々の予習方法について詳しく解説しています。
興味のある方はチェックしてみてください。
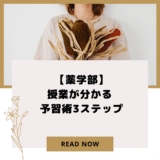 【薬学部】 授業が分かる予習術3ステップ
【薬学部】 授業が分かる予習術3ステップ
鉄則③ 授業中のメモは“宝の山”になる
話を聞きながらメモを取るクセをつける
教授の発言には、試験に出る情報が
たくさん隠されています。
「ここ、大事ですよ(試験に出しますね)」
なんて言われた日には、マーカー必須です。
スライドを写すだけではなく、教授の
補足説明や板書、雑談の中にヒントがあることも珍しくありません。

中には板書せずに口頭で話しただけの内容を出題する輩もいます。(けしからん!)
メモの取り方で理解が変わる
ただ書くだけでなく、“自分の言葉で
書き直す”のがポイントです。
メモをもとに自分なりのまとめノートを作ると、復習時の理解度が格段にアップします。
- 「なんでこうなるの?」
- 「この単語ってどこに繋がるの?」
と、自分で問いかけながら書くと、
記憶にも残りやすくなります。

漫然とメモを取るよりも
記憶に残りやすいです。
まとめ|この3つを押さえておけば合格は見える
薬学部の定期試験を乗り切るには
ただ闇雲に勉強するのではなく、
戦略的に取り組むことが大切です。
今回紹介した3つの鉄則をおさらいすると
- 鉄則①:過去問を最大限に活用する
- 鉄則②:シラバスをしっかり読み込む
- 鉄則③:授業中のメモを大切にする
この3つを軸にすれば、限られた時間でも
結果を出せる勉強が可能になります。
定期試験の勉強を通じて結果を出せる勉強方法を経験しておけば、
薬剤師国家試を合格するための基礎にも
なります。
早いうちから“結果を出せる勉強方法”を
習慣化して、強い自信と実力をつけていきましょう!
こちらの記事でも
定期試験の準備について解説しています。
勉強スケジュールの立て方など、
今回紹介した「3つの鉄則」以外の部分に
ついて解説しているので、
興味のある方は
チェックしてみてください。
 薬学部の定期試験に備えて~効率よく勉強していく方法について解説~
薬学部の定期試験に備えて~効率よく勉強していく方法について解説~
最後に
試験後に使い終わった教科書を処分する
となった時に、そのまま捨てる人も多いと思います。
しかし、そのまま捨てるのは
非常にもったいないです!
薬学部の教科書は高かったんだから、
少しでもお得に処分した方が絶対良いはずです。
そこで、賢く・お得に教科書を処分する
方法について、下の記事で解説しています。
「ちょっとでもお得に処分したいな~」と考えている方は、ぜひチェックしてみてください!
 薬学部の教科書を賢く処分|売却の完全ガイド
薬学部の教科書を賢く処分|売却の完全ガイド
以上、「【薬学部】定期試験に合格する3つの鉄則」という話題でした!